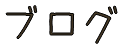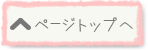勝興寺、平成の大修理の棟梁、田中健太郎さんに取材したのは8年前。
大工道具を見せてほしいと頼むと、棟梁は現場事務所にあった会議机を全部寄せ始めた。
その上に白い布をかぶせ、即席の展示台が出来上がると、若い職人さんが道具の入った大きな木の箱を肩に担いで次々と運んできた。
棟梁は箱から数々の大工道具を取り出し並べ始め、畳3枚分くらいあった展示台がみるみる埋まっていった。
鉋(カンナ)だけでも、まな板くらいの大きなものから、ライターほどの小さいサイズまで揃っていて、形状も様々。鋸(ノコギリ)、鑿(ノミ)、手斧(ちょうな)、指矩(さしがね)、墨壺・・・と、その数と種類に目を見張った。中には、刃の部分がかなり短くなった鑿があって尋ねると、見習いの時からずっと使い続けていて、研いでいるうちにそうなったと教えてくれた。
それら道具全てが、田中棟梁の大工人生を物語っていた。
当時、田中棟梁の元で修行していたのが山室さんと堀井さん。二人とも高岡工芸高校の建築科を卒業した20代半ばの若い大工さんだった。
驚いたことに、二人とも技能五輪全国大会で銀賞に輝いているのだ。
技能五輪全国大会は、毎年取材で見ているが、建築大工の競技課題は相当難しく、電動工具に頼らない本物の技量に加え、図面を全て記憶する能力も問われ、完成させることすら簡単ではない。
この大会に出る選手は皆、数か月から1年かけて競技課題を練習するのが普通だが、山室さんも堀井さんも特別な練習をしたわけでもなく、勝興寺の現場で、「田中棟梁から教わったことをそのまま競技でやっただけ」と言っていた。
「国宝」となり、その歴史的価値が全国に知られるのは喜ばしいことだが、一方で、日本の誇りである文化財を後世に遺し続ける責任は大きい。しかし、それを担う技能人を育てていく体制というのはかなり脆弱だ。
元来、日本は職人の国だった。大工のかしらは「棟梁」と呼ばれ、あらゆる知識と技能に長けたリーダーの代名詞であり、誰からも尊敬を集めた。だからこそ、若い職人は棟梁の下で厳しい修行に耐え、年季奉公も厭わなかった。時代が変わり、棟梁と呼ばれる人たちは高齢化の一途をたどり、後に続く若い技能人は先細っている。
そうなる理由としてはいろいろあるが、信じ難いことに、建築業界で「職人」と呼ばれる人たちの雇用形態は、現在でも日給月給(いわば日当)が大半であり、仕事に誇りを感じてはいても、現実と狭間で辛さを感じる若い職人が多い。その問題をなぜ解決できないのか。これを語り出すときりがなく、ひとことで言ってしまえば、「都合がいいから」ということになるが、一方で、「職人を長く続ければ、やめられなくなる」という一面があるのも事実である。それはどうしてなのか?これまで職人さんを数多く取材してきてわかる気がする。
ある棟梁はこう言っていた。
「先輩の職人から『おくがなら(辞めるなら)今やぞ。もうちょっこ経ったら、おかれんがなるげんぞ!』と言われた。その意味がわかったのは、少し仕事ができるようになった頃。だんだん大工の良さがわかってくると、やめられんようになるんやね。例えば、ものが思い通りにピシッと納まると、もう最高やさけぇね。「また次も」って、やめられんようなる (笑)。失敗も何回もするけど、 あのピタッと合ったときの快感いうたら特別。それが職人ちゅうもん。今、49年目やけど、まだ半人前やと思うとる」。
確か、勝興寺の田中棟梁もこんなことをおっしゃっていたのを思い出す。
「高校を出てから20年以上大工をやってきて名前も知られるようになったけど、ずっと満たされない思いがあった。それは宮大工へのあこがれ。大工として、本当の技量の高さが表に出る宮大工にどうしてもなりたかった」。
新聞によると田中棟梁は現在、療養中とのことだったが、勝興寺の改修中も子供たちを現場に招き、「子供大工教室」を行なっていらっしゃった。子供たちの手に取らせる鋸(のこぎり)などの道具は自分が使っているもの。「本物に触れさせなければ伝わらない」とおしゃっていたことを思い出した。